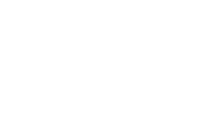梅雨の養生
2023/07/03
7月を迎え、梅雨明けはまだもう少し。
今回は梅雨の養生について少しお話ししたいと思います。
皆さんは五臓六腑という言葉を聞いた事はありますか?
(中医学の五臓六腑の考え方、現代の西洋医学とは少し異なります。)
五臓 肝・心・脾・肺・腎
身体に必要なエネルギーの生成や流通、貯蔵を行っています。
六腑 胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦
身体の生理機能を営んでいます。
五臓と六腑は表裏関係にあり、五臓はそれぞれ他の臓に影響を及ぼしあっており、このバランスを崩すと身体の不調や病気になると考えられています。梅雨の時期は消化器系である脾と胃が活発になります。脾は、消化した物を栄養になるように変化させ、運ぶ役割をしています。中医学では消化して運ぶという意味で、運化といいます。気・血・精・津液を生成し、内臓や四肢、被毛や筋肉を営養する重要な役割を担っています。この脾の特徴は、運化を保つため乾燥を好み、湿気を嫌います。なので脾は梅雨がとても苦手なのです。
この時期、消化不良や食欲不振、疲れやすさや無気力感、浮腫みやすいなど感じた事はありませんか?
それは湿気を嫌う脾が、キチンと働けていないのが原因の一つ。湿気の邪気、湿邪は陽気を傷つけ気の流れも阻害してしまうのです。更に梅雨の蒸し暑さから、冷たい物、生もの、水分も多く摂りがちなので、余計脾は疲れてしまいがち。梅雨時期の食養生は、余分な湿が溜まらないようにし、脾を養う事が大切になります。
ここで、手にはいりやすい湿を発散させる食材を幾つかご紹介します。
とうもろこし、ハト麦、黒豆、大豆、生姜、葱、紫蘇、三つ葉、さくらんぼ、うど、しじみ、はまぐり、長芋、鶏肉、米、キャベツ etc
利尿作用であったり、脾胃の働き強化であったり、香り成分や苦味成分、辛み成分だったりと、それぞれ湿の取り方に違いはありますが、身近な食材ですよね。このような食材をうまく取り入れ、身体をしっかり養い、風通しを良くし、このジメジメした梅雨を楽しく乗り切りましょう!!

〇鶏肉のはと麦あんかけ・・・気を補い脾胃を養い、湿邪を取り除きます

〇コーンスープ枝豆のせ・・・利尿作用で湿邪を取り除き、気の巡りをよくします