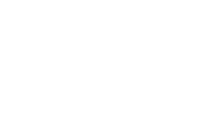冬の養生
2024/01/15
日が短く寒い日が続いています。今回は冬の養生についてお話ししたいと思います。
冬は立冬から立春までの三か月間、中医学では陰気旺盛という言葉で表されます。
冬の気候は寒さの邪気、寒邪となります。寒邪の特徴は陰邪で陽気を傷つけやすく、冷えや下痢、悪寒などの症状を引き起こします。
その他にも体が固くなりやすく、頭痛や関節痛、足腰の痛みなどの症状がみられます。身体が縮こまりやすく、筋肉や筋脈、関節などが痙攣を起こし、四肢の屈伸がしにくくなったり、気管支炎や心筋梗塞などの発病率が高くなる傾向があります。
冬の時期は腎の働きが活発になるので、腎を養うと良いとされています。各臓腑は一年中よく働き、気・血・津液を消耗していますが、その元となる精気は腎に貯蔵されています。腎は成長、発育、生殖を促進する働き、髄を化生し、骨を滋養、脳に繋がり歯に関連するのです。その為冬はしっかりと飲食して栄養を貯蔵し、各臓腑に届けて身体を養う必要があります。そしてきちんと寝て、陽気を逃さないよう身体を温める必要があります。
冬の食養生は、腎を養い乾燥に注意、保温を心掛け免疫力をつけるようにすると良いでしょう。ここで、手にはいりやすい食材を幾つかご紹介します。
・気を補い、陽を温め身体を補助する食材
粳米、もち米、鶏肉、じゃがいも、栗、いんげん、長芋、しいたけ
・内臓を温め、寒気を散らす食材
生姜、羊肉、鹿肉、海老、ニラ、山椒
・気を巡らせ血流を良くする食材
酢、蕎麦、らっきょう、みかん、グリーンピース、チンゲン菜
・血を養い陰を補う食材
胡麻、ほうれん草、いか、豚レバー、鶏レバー、人参、落花生、牡蠣、ムール貝
この他にも腎と表裏関係にある膀胱を養い、冬の五色である黒い食材等を積極的に摂り、寒い冬を美味しく乗り切りましょう!

(ほうれん草の胡麻和え、黒豆の甘酒煮、発酵玄米)