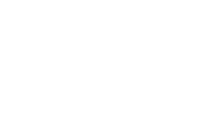日本酒の歴史
2024/04/12
今回は日本酒の歴史のお話しです。
米を原料とする酒造りがいつごろから始まったのかは定かではありません。しかし大陸からの稲作の伝来に伴って伝えられたのではないかと考えられています。
『魏志倭人伝』には3世紀ころには既に飲酒の習慣があった事が記されています。『大隅風土記』には、口噛酒があったとなっています。
口噛酒とは、米を噛んでつくられる物で唾液中に含まれるでんぷんの分解酵素を利用し、でんぷんをブドウ糖に変え、空気中にある酵母が侵入してアルコール発酵が自然に起こるのを待つ原始的な酒造りです。数年前に流行った”君の名は”の劇中に登場したので、ご存知の方も多いかもしれません。因みにワインなどは猿噛み酒、つまりは野生動物が葡萄を噛む事により同じくアルコール発酵が起きた?!などと言われています。
『播磨風土記』には、干し飯が水に濡れてカビが生えた(今で言う麹のような物)のを利用し酒を造らせたとの記述があります。これは麹菌の糖化作用を利用した醸造方法であり、現代の製造方法と通じるものがあります。
この様に奈良時代の同時期に2つの異なった醸造方法が記されています。因みにお酒の醸造を”醸す”と言いますが これは ”噛む”に由来するともカビの生えた状態をいう”カビ立ち” に由来するとも言われています。
その後お酒の醸造は奈良、平安時代を通じて朝廷や僧坊で行われ、次第に民間へと広がっていきます。そして中国や朝鮮から酒母つくりや醪の三段仕込み法、火入れ殺菌法が伝わり、醸造方法が改良されていきました。
しかし、中国で使用される麹はクモノスカビなどを生育させてできますが、日本は蒸した米に麹菌を繁殖させる点で違いがあり、伝来した技術を改良して日本古来の清酒が誕生しました。朝廷では造酒司を設けました。酒は神事に欠かせない付き物で、朝廷や寺社が中心で造られ、寺院で造られた僧坊酒は高い評価を得るようになったと言われています。
次回はその後の清酒の歴史について触れていきます。