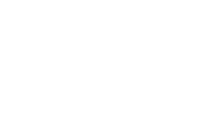コラム
日本酒の歴史~その2
2024/07/16
前回、朝廷では造酒司を設け、朝廷や寺社が中心で造られた日本酒ですが、寺院で造られた僧坊酒は高い評価を得るようになった事をお伝えしました。今回は日本酒発祥の地を取り上げたいと思います。
寺院では鎮守や天部の仏へ献上するお酒として、荘園からあがる米を用いてお酒を自家製造していました。このように荘園でつくられた米を僧侶が用いて醸造するお酒が僧坊酒です。多い時には120坊を抱え、大量の僧坊酒を造る大寺院であったのが正歴寺です。正歴寺は、奈良市東南の郊外の山間にあるお寺で、992(正歴3)年、一条天皇の勅命を受けて兼俊僧正(藤原兼家の子)によって創建されました。
当時の正歴寺では「三段仕込み」や、現代で言う酒母の原型となる「菩提酛(ぼだいもと)造り」、掛米と麹の両方に白米を使用する「諸白造り」、腐敗を防ぐ為に行われる「火入れ作業」等を行っていました。まさに近代の醸造の基礎となる技術が確立されていたのです。これらの酒造技術は革新的な酒造方法として、室町時代「御酒之日記」や江戸時代初期「童豪酒造記」などの古文書にも記され、脈々と受け継がれていきました。
このように正歴寺の酒造技術は非常に高く、天下第一と評される「南都諸白」に受け継がれていきます。
〈南都諸白〉
数ある僧坊酒の中で、室町時代に至るまで長い事高い名声を保った酒の事。諸白とは、現在の酒造りの基礎になっている、麹米と掛け米の両方に精白米を用いる手法で造られた透明度の高い酒。現在の清酒とほぼ等しい酒の事を、当時の主流を占めていた濁り酒に対して呼んだ名称。江戸時代以降も「下り諸白」などのように、上級酒を表す言葉として使用された。
この「諸白」こそが現代の日本酒造りの祖とされています。この様な歴史的背景から、正歴寺が日本酒醸造の原点であると言われている所以であります。現代と殆ど変わらない製法が千年を超える昔からあったとは、当時の技術と知恵に驚かされます。正歴寺では、現在でも酒母の仕込みを年に一度冬に行っているそうです。